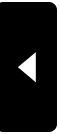スポンサーサイト
車載モニターと車検対応
2009年12月23日
ご愛車に取り付けたいろいろカー製品で気になるのは車検対応だろう。
車載モニター の場合、シートの一部を改変してしまうヘッドレストモニター は、そのままでは車検対応外なのだが、カバーを装着して隠してしまえば車検も合格するようだ。
フレーダーマウスのヘッドレストモニターには、ヘッドレストモニターカバーが用意されているので、安心してヘッドレストモニターを装着する事が出来る。しかし、ヘッドレストモニターの装着には、シート内部に配線を通す必要があり、器用な方なら問題ないだろうが、個人でヘッドレストモニターを装着するにはかなりの勇気とコツが必要だ。
バイザーモニター も同様に、装着自体はサイズさえ合えば簡単なのだが、ヘッドレストの位置と限られている為、車載モニターまでの配線に苦労する。車体のフレームに沿ってフロントコンソールの裏へうまく配線できれば良いのだが、配線が露出してしまうと、せっかくのマルチ車載モニターの雰囲気も台無しだ。
最後にフリップダウンモニター だが、フリップダウンモニターこそ車載モニターの醍醐味といえる存在だろう。車内天井から引き出されるフリップダウンモニターの大画面は、車載モニターの中核をなす存在感が感じられるだろう。また、通常の走行時など必要の無いときには、フリップダウンモニターは簡単に格納できる事もうれしい事だ。しかし、この重要なフリップダウンモニターの装着は、一般の個人レベルでは多少難しいかもしれない。まず室内ランプがちょうど良い位置にあれば、ランプのステーを取り外し、そこにフリップダウンモニターを装着すればよいのだが、通常ドアの開閉などに連動してランプが付くだけの仕掛けのルームランプへの配線は、細い電線が通っているだけだ。しかしフリップダウンモニターを装着するとなると、車載モニターへの電源供給だけでなく、映像信号を取るための配線も必要となる。それには、通常の電源用配線よりも太くて丈夫な映像信号用のケーブルを配線しなくてはならないからだ。また、ルームランプが天井に無い車種となると、フリップダウンモニターは、直接車体のフレームを構成する天井の梁に取り付けねばならない。この作業は、下手をすると車体強度を失うだけでなく、取り付けの金具やネジで車体の屋根自体を傷つけてしまうかもしれないからだ。フリップダウンモニターの装着は慣れた業者に相談する方がいいだろう。
車載モニター の場合、シートの一部を改変してしまうヘッドレストモニター は、そのままでは車検対応外なのだが、カバーを装着して隠してしまえば車検も合格するようだ。
フレーダーマウスのヘッドレストモニターには、ヘッドレストモニターカバーが用意されているので、安心してヘッドレストモニターを装着する事が出来る。しかし、ヘッドレストモニターの装着には、シート内部に配線を通す必要があり、器用な方なら問題ないだろうが、個人でヘッドレストモニターを装着するにはかなりの勇気とコツが必要だ。
バイザーモニター も同様に、装着自体はサイズさえ合えば簡単なのだが、ヘッドレストの位置と限られている為、車載モニターまでの配線に苦労する。車体のフレームに沿ってフロントコンソールの裏へうまく配線できれば良いのだが、配線が露出してしまうと、せっかくのマルチ車載モニターの雰囲気も台無しだ。
最後にフリップダウンモニター だが、フリップダウンモニターこそ車載モニターの醍醐味といえる存在だろう。車内天井から引き出されるフリップダウンモニターの大画面は、車載モニターの中核をなす存在感が感じられるだろう。また、通常の走行時など必要の無いときには、フリップダウンモニターは簡単に格納できる事もうれしい事だ。しかし、この重要なフリップダウンモニターの装着は、一般の個人レベルでは多少難しいかもしれない。まず室内ランプがちょうど良い位置にあれば、ランプのステーを取り外し、そこにフリップダウンモニターを装着すればよいのだが、通常ドアの開閉などに連動してランプが付くだけの仕掛けのルームランプへの配線は、細い電線が通っているだけだ。しかしフリップダウンモニターを装着するとなると、車載モニターへの電源供給だけでなく、映像信号を取るための配線も必要となる。それには、通常の電源用配線よりも太くて丈夫な映像信号用のケーブルを配線しなくてはならないからだ。また、ルームランプが天井に無い車種となると、フリップダウンモニターは、直接車体のフレームを構成する天井の梁に取り付けねばならない。この作業は、下手をすると車体強度を失うだけでなく、取り付けの金具やネジで車体の屋根自体を傷つけてしまうかもしれないからだ。フリップダウンモニターの装着は慣れた業者に相談する方がいいだろう。
Posted by mikoqi at
10:12
│Comments(0)
カーオーディオ
2009年12月21日
カーオーディオ(Car Audio)は自動車に搭載されるオーディオ機器のことで「カーステレオ」ともいわれる。
初期のカーオーディオは米国の「ガルビン・コーポレーション」が1930年に製作したカーラジオから始まった。これは、モトローラ5T71型という名前であり、モトローラとは、モーター(自動車)のオーラ(音)という意味である。この会社はのちこの名前を社名にした。同じく米国ゼネラルモーターズ傘下では子会社デルコ・エレクトロニクスが1936年にダッシュボード内に装着したカーラジオを製作する。ラジオによる移動中の情報入手や音楽放送の楽しみはあったがドライバーや同乗者ができるのは好きな放送局を選ぶことだけであった。
しばらくして、自分の好きな音楽を聴きたいときに聴ける仕組みができた。音声用磁気テープを使用したものとしては、最初に4トラックカートリッジが1964年(開発元のある米国では前年の1963年)に発売される。寸法は後述の8トラックとほぼ同じであるが、ピンチローラーは再生機側に搭載されている。またプログラム切り替えは当初手動のみであった。その後自動切り替え機能を搭載した機種も発売されたが、日本市場では本格的な普及には至らなかった。次に現れたのが初期のカラオケシステムで使用された8トラックカートリッジである。しかし当時のオーディオソースの主流はレコードであり、気に入った歌でも家庭で聞くためのレコードと車で聴くための8トラックカートリッジとそれぞれ別に購入するのが一般的だった。録音用生テープや録音用機器もあるにはあったが、主流は家庭ではレコードプレーヤーとコンパクトカセットであり、その上に録音用8トラック機器の購入というのはよほどの好き者であった。この他にも、70年代にはパイオニアからハイパックというカセットテープ大のエンドレスカートリッジを採用したカーオーディオも発売されたが、元となったプレーテープ規格と同じく収録時間の短さや一般ユーザー向けに録音機器が出なかったこともあり、数年の間に姿を消した。
1970年代前半まではAMチューナーのみが主流であり、主要車種に設定される「デラックス」グレードに標準装備されることも多かった。同時期からFMチューナー搭載機種が増え始め、電子チューナーも登場した。
2000年代になるとカーナビゲーションシステムが普及してきたことで、それまでディスプレイ部分に採用されていたFL管や発光ダイオードに加えて液晶車載モニターを組み込んだ一体型も多くなり、操作ボタンもタッチパネルが多くなってきた。
初期のカーオーディオは米国の「ガルビン・コーポレーション」が1930年に製作したカーラジオから始まった。これは、モトローラ5T71型という名前であり、モトローラとは、モーター(自動車)のオーラ(音)という意味である。この会社はのちこの名前を社名にした。同じく米国ゼネラルモーターズ傘下では子会社デルコ・エレクトロニクスが1936年にダッシュボード内に装着したカーラジオを製作する。ラジオによる移動中の情報入手や音楽放送の楽しみはあったがドライバーや同乗者ができるのは好きな放送局を選ぶことだけであった。
しばらくして、自分の好きな音楽を聴きたいときに聴ける仕組みができた。音声用磁気テープを使用したものとしては、最初に4トラックカートリッジが1964年(開発元のある米国では前年の1963年)に発売される。寸法は後述の8トラックとほぼ同じであるが、ピンチローラーは再生機側に搭載されている。またプログラム切り替えは当初手動のみであった。その後自動切り替え機能を搭載した機種も発売されたが、日本市場では本格的な普及には至らなかった。次に現れたのが初期のカラオケシステムで使用された8トラックカートリッジである。しかし当時のオーディオソースの主流はレコードであり、気に入った歌でも家庭で聞くためのレコードと車で聴くための8トラックカートリッジとそれぞれ別に購入するのが一般的だった。録音用生テープや録音用機器もあるにはあったが、主流は家庭ではレコードプレーヤーとコンパクトカセットであり、その上に録音用8トラック機器の購入というのはよほどの好き者であった。この他にも、70年代にはパイオニアからハイパックというカセットテープ大のエンドレスカートリッジを採用したカーオーディオも発売されたが、元となったプレーテープ規格と同じく収録時間の短さや一般ユーザー向けに録音機器が出なかったこともあり、数年の間に姿を消した。
1970年代前半まではAMチューナーのみが主流であり、主要車種に設定される「デラックス」グレードに標準装備されることも多かった。同時期からFMチューナー搭載機種が増え始め、電子チューナーも登場した。
2000年代になるとカーナビゲーションシステムが普及してきたことで、それまでディスプレイ部分に採用されていたFL管や発光ダイオードに加えて液晶車載モニターを組み込んだ一体型も多くなり、操作ボタンもタッチパネルが多くなってきた。
Posted by mikoqi at
15:34
│Comments(0)
フリップダウンモニター不具合のサポート
2009年12月17日
今回は、フリップダウンモニターの不具合について話します。
モニターというと、大体一緒です。(オンダッシュ、インダッシュでも一緒です。)
状況によって原因が異なります。以下に代表的な症状を挙げますので、ご確認ください。
例1 電源を入れると、モニターにブルー画面が表示される場合
映像信号が正常にモニターに届いていません。もう一つのビデオ入力端子に繋いでみて頂くか、分配器を使用して映像出力を安定させて頂ければ、改善する場合があります。
例2 電源を入れても、モニター画面は真っ黒のまま、または真っ白になる場合
真っ黒の場合
*電圧が正常範囲内ですか。
*電源ランプが点灯していますか。
問題がない場合は、一度電源を切ってから、再接続してみてください。
真っ白な場合
主に内部異常が原因として考えられます。
どちらの場合も、本体の故障、不良の可能性がございます。
モニターというと、大体一緒です。(オンダッシュ、インダッシュでも一緒です。)
状況によって原因が異なります。以下に代表的な症状を挙げますので、ご確認ください。
例1 電源を入れると、モニターにブルー画面が表示される場合
映像信号が正常にモニターに届いていません。もう一つのビデオ入力端子に繋いでみて頂くか、分配器を使用して映像出力を安定させて頂ければ、改善する場合があります。
例2 電源を入れても、モニター画面は真っ黒のまま、または真っ白になる場合
真っ黒の場合
*電圧が正常範囲内ですか。
*電源ランプが点灯していますか。
問題がない場合は、一度電源を切ってから、再接続してみてください。
真っ白な場合
主に内部異常が原因として考えられます。
どちらの場合も、本体の故障、不良の可能性がございます。
Posted by mikoqi at
13:23
│Comments(0)
車載製品
2009年12月14日
マイカーの車内をゴージャスにドレスアップするには、見た目の迫力もさることながら、車内に車載モニターを多数配置するのが良い。現在多く流通している車載モニターには、ヘッドレストモニター、フリップダウンモニター、サンバイザーモニターがあり、ミニバンやワゴン車で、7人乗りや8人乗りなら、7つか8つのヘッドレストモニターが設置可能。
更に運転席と助手席の前にはバイザーモニターが設置可能。止めに車内中央に大型のフリップダウンモニターを設置すれば、自動車の室内には映像が溢れ、癒しの空間に大変身するだろう。 コンピュータ用でも同じであるが、最近は車載モニターの価格が急激に低下している。これは車載モニターの製品価格にも影響を与え、数年前までは高値の花だった液晶モニターが僅か数万円で、複数台揃えられる状況だ。
フレーダーマウスオリジナルの車載モニター製品は、シートカバー製品に合わせ、ブラック、ベージュ、クロコダイル調のレーザーベースのものが用意され、ヘッドレストモニターは2台で税込\23,100から、フリップダウンモニターは税込\17,850から、バイザーモニターは2台で税込\12,600となっている。これだけで、車載モニターが5台揃う事になるのだが、総額で5万円強しかかからない。更に後部座席全てにヘッドレストモニターをセットしても約8万円だ。この状態だと車載モニターは9台となる。そうなると映像の出力分配も多数必要となり、8分配の映像分配器を追加しても足りないかもしれない。
更に運転席と助手席の前にはバイザーモニターが設置可能。止めに車内中央に大型のフリップダウンモニターを設置すれば、自動車の室内には映像が溢れ、癒しの空間に大変身するだろう。 コンピュータ用でも同じであるが、最近は車載モニターの価格が急激に低下している。これは車載モニターの製品価格にも影響を与え、数年前までは高値の花だった液晶モニターが僅か数万円で、複数台揃えられる状況だ。
フレーダーマウスオリジナルの車載モニター製品は、シートカバー製品に合わせ、ブラック、ベージュ、クロコダイル調のレーザーベースのものが用意され、ヘッドレストモニターは2台で税込\23,100から、フリップダウンモニターは税込\17,850から、バイザーモニターは2台で税込\12,600となっている。これだけで、車載モニターが5台揃う事になるのだが、総額で5万円強しかかからない。更に後部座席全てにヘッドレストモニターをセットしても約8万円だ。この状態だと車載モニターは9台となる。そうなると映像の出力分配も多数必要となり、8分配の映像分配器を追加しても足りないかもしれない。
Posted by mikoqi at
15:56
│Comments(0)
サンバイザーモニター取付方法
2009年12月09日
主な使用工具・・・
プラスドライバー
マイナスドライバー(内張り外し用)
ギボシ(圧着コネクター)
ビニールテープ
●サンバイザーモニターのシャフトを伸縮調整し車輌の取付幅に合わせる。
※両手で本体とシャフトを持ち前後にひねりながら伸縮させる
●サンバイザーの取付位置を確認する
●サンバイザーを外す。
●ドア骨格のゴム(モール)を外し内張り外し等でAピラーを外す。
●Aピラーを外す。
●受け側のフックを取り付ける。
●サンバイザーのネジ穴に天張りを少し浮かせ本体配線を通す。
●純正のネジ穴を使用し本体を取り付ける。
※ネジを必要以上にまわすとシャフトが配線を圧迫し断線する可能性があります。シャフトの配線出口部分をビニールテープ等で 補強することをお勧めいたします。
●本体配線と付属配線のコネクターを矢印の部分で結合し ビニールテープで補強する。
●配線をAピラー、ダッシュボードの脇に沿わせ隠す。
●付属配線側の映像線(黄、白のRCA)を映像入力する。電源(赤:アクセサリー) ・アース(黒:ボディー等)のそれぞれをギボシ端子等を利用し確実に取り付ける。(14)
●バックカメラをV2(白のRCA)に入力する際は緑の配線をバックライト線(後退時に点灯するライト配線)にギボシ端子等を利用し確実に取り付ける。
●本体電源を入れ動作確認をする。映像や機能に問題が無ければAピラーを戻して完成。
Posted by mikoqi at
19:55
│Comments(0)
DVDプレーヤー紹介
2009年12月07日
DVDプレーヤーはテレビに接続して視聴する。DVDプレーヤー単体製品のほか、レーザーディスク (LD) とのコンバチブルプレーヤー、VHSとの一体型(一部の製品は、S-VHSにも対応)などがある。またCDと同様にディスクサイズが12cmと小型であるため、ラジカセやカーオーディオ、カーナビゲーションでもDVDの再生が可能な機種がある。液晶ディスプレイやスピーカーを搭載し、可搬性のあるポータブルDVDプレーヤーもある。内蔵バッテリーにより、単体でもおおむね2時間程度の再生が可能である。
DVD普及の立役者となったDVD対応ゲーム機プレイステーション2
DVDの再生のほか録画も可能なDVDレコーダー最初のDVDプレーヤー(据え置き型)は1996年に発売された。当初は最も下位の機種でも6~8万円程度と高価であったことや、対応ソフトの少なさから普及の出足は鈍かった。
2000年にDVD-Video再生対応のゲーム機「プレイステーション2」(当初の標準価格は39800円)が発売されてから、それまで高価だったDVDプレーヤーの低価格化が進み、DVDソフトの普及が一気に進んだ。以後日本で発売されたゲーム機ではQ(ゲームキューブの派生機種)、Xbox、Xbox 360、プレイステーション3がDVD-Video再生に対応している。
日本国内では、2003年頃からDVDレコーダーの本格的な普及が始まったため、据え置き型のDVDプレーヤーの市場は、コモディティ化して安価なプレーヤーが出回るなど安定普及期を過ぎつつある。ただし、欧米を含む海外では、現在でもレコーダーよりも需要が高い。DVDプレーヤーの生産台数は中国が世界最多である(2002年において3000万台、全世界でシェア70%)。日本市場向けとして開発される製品にはフジエアーの例のように誤植が目に付くことがある。なお、中国国内のメーカーは、MPEG-2のライセンス使用料とDVD特許料として1台あたり約2000円程度のコストが掛かっている。そのため回避策としてEVDという独自の光ディスク規格を開発した。現在、EVD規格は中国国内でのみ採用されている。
DVD普及の立役者となったDVD対応ゲーム機プレイステーション2
DVDの再生のほか録画も可能なDVDレコーダー最初のDVDプレーヤー(据え置き型)は1996年に発売された。当初は最も下位の機種でも6~8万円程度と高価であったことや、対応ソフトの少なさから普及の出足は鈍かった。
2000年にDVD-Video再生対応のゲーム機「プレイステーション2」(当初の標準価格は39800円)が発売されてから、それまで高価だったDVDプレーヤーの低価格化が進み、DVDソフトの普及が一気に進んだ。以後日本で発売されたゲーム機ではQ(ゲームキューブの派生機種)、Xbox、Xbox 360、プレイステーション3がDVD-Video再生に対応している。
日本国内では、2003年頃からDVDレコーダーの本格的な普及が始まったため、据え置き型のDVDプレーヤーの市場は、コモディティ化して安価なプレーヤーが出回るなど安定普及期を過ぎつつある。ただし、欧米を含む海外では、現在でもレコーダーよりも需要が高い。DVDプレーヤーの生産台数は中国が世界最多である(2002年において3000万台、全世界でシェア70%)。日本市場向けとして開発される製品にはフジエアーの例のように誤植が目に付くことがある。なお、中国国内のメーカーは、MPEG-2のライセンス使用料とDVD特許料として1台あたり約2000円程度のコストが掛かっている。そのため回避策としてEVDという独自の光ディスク規格を開発した。現在、EVD規格は中国国内でのみ採用されている。
Posted by mikoqi at
19:11
│Comments(0)
ヘッドレスモニター&配線
2009年12月03日
配線について
ヘッドレスモニターをノ配線についてですが、車に取り付ける際の配線は、ヘッドレストモニターのシャフトの中から電源および外部入力1の配線が出ていますから、配線を背もたれについている穴に入れて、押し込んでいきます。
途中で10センチから15センチくらい入ったところで少し引っかかると思いますが、何度も根気よく押していくうちに、するっと下のほうにヘッドレストモニターの配線がおちると思います。
その跡に、外部入力の2の配線はモニターの下の部分から露出することになります。
下のほうにでてきた配線は、背もたれの下のシートの生地の隙間の部分から指を入れて引っ張って出してください。
RCA入力と、電源はバイザーモニターの部分から分岐して接続するといいでしょう。ヘッドレストやシートの中を配線するというのは、少し難しいと思うのですが、
最近ではブログやサイトにて、ヘッドレストモニターの配線方法を公開してくれているところもありますから覗いてみるといいかもしれません。
ヘッドレストモニターの配線は、見た目にわからないように仕上げるのがいいと思います。ヘッドレストシャフトのなかに通すことで配線をしたことがわかりにくくて綺麗です。
ヘッドレスモニターをノ配線についてですが、車に取り付ける際の配線は、ヘッドレストモニターのシャフトの中から電源および外部入力1の配線が出ていますから、配線を背もたれについている穴に入れて、押し込んでいきます。
途中で10センチから15センチくらい入ったところで少し引っかかると思いますが、何度も根気よく押していくうちに、するっと下のほうにヘッドレストモニターの配線がおちると思います。
その跡に、外部入力の2の配線はモニターの下の部分から露出することになります。
下のほうにでてきた配線は、背もたれの下のシートの生地の隙間の部分から指を入れて引っ張って出してください。
RCA入力と、電源はバイザーモニターの部分から分岐して接続するといいでしょう。ヘッドレストやシートの中を配線するというのは、少し難しいと思うのですが、
最近ではブログやサイトにて、ヘッドレストモニターの配線方法を公開してくれているところもありますから覗いてみるといいかもしれません。
ヘッドレストモニターの配線は、見た目にわからないように仕上げるのがいいと思います。ヘッドレストシャフトのなかに通すことで配線をしたことがわかりにくくて綺麗です。
Posted by mikoqi at
13:38
│Comments(0)
ルームミラーモニター取付
2009年12月01日
ヘッドレストモニターのみでも十分、後席の人のエンターテイメント性は向上しますが、ドレスアップのモニターメイクとして、ミラーモニターも装着した方がいいとおもいます。
一般的にルームミラーモニター本体の他に、電源・映像配線、リモコンが付属されています。ルームミラーモニターではほとんどの製品に映像入力が2つ用意されています。1つはDVDなどのビデオ用。もう一つはバックモニター用です。2つ目のバックモニター用も使い方によってはDVDビデオの映像を流すことも可能です☆電源はACC電源とアース、それとバックギヤに連動させるためのリーバース信号線です。映像信号線がこちら。AV1とAV2があります。DVDプレーヤーなどの映像信号線はAV1に、バックモニターの映像信号線はAV2にそれぞれ繋ぎます。
リモコンは電源ON-OFFの他に画面の明るさやコントラスト。それに映像の左右反転、上下反転も操作できます。運転席からは本体に手が届きますが、リヤシートの人からは届かないのであると便利なアイテムですね。
本体にも大体メニュー、画面調整の+、画面調整の-、電源の4つのボタンがあります。またリモコン受信センサーが搭載されているはずです。
取り付けはアクセサリー電源、アース、映像コードのみを接続するだけで、基本的には簡単です。
ルームミラーモニターはヘッドレストモニターなどと比べると価格が安いので、ナビなしでバックモニターを付けたい人なんか特にオススメですね。海に行った帰りにデジカメの写真をスライドショーしたり、お気に入りの写真を表示させたり、色んな使い方ができると思います。
一般的にルームミラーモニター本体の他に、電源・映像配線、リモコンが付属されています。ルームミラーモニターではほとんどの製品に映像入力が2つ用意されています。1つはDVDなどのビデオ用。もう一つはバックモニター用です。2つ目のバックモニター用も使い方によってはDVDビデオの映像を流すことも可能です☆電源はACC電源とアース、それとバックギヤに連動させるためのリーバース信号線です。映像信号線がこちら。AV1とAV2があります。DVDプレーヤーなどの映像信号線はAV1に、バックモニターの映像信号線はAV2にそれぞれ繋ぎます。
リモコンは電源ON-OFFの他に画面の明るさやコントラスト。それに映像の左右反転、上下反転も操作できます。運転席からは本体に手が届きますが、リヤシートの人からは届かないのであると便利なアイテムですね。
本体にも大体メニュー、画面調整の+、画面調整の-、電源の4つのボタンがあります。またリモコン受信センサーが搭載されているはずです。
取り付けはアクセサリー電源、アース、映像コードのみを接続するだけで、基本的には簡単です。
ルームミラーモニターはヘッドレストモニターなどと比べると価格が安いので、ナビなしでバックモニターを付けたい人なんか特にオススメですね。海に行った帰りにデジカメの写真をスライドショーしたり、お気に入りの写真を表示させたり、色んな使い方ができると思います。
Posted by mikoqi at
16:56
│Comments(0)
ワンセグチューナー
2009年11月26日
ワンセグとは、2006年4月1日から開始された、地上デジタルテレビ放送の一つで、13セグメントに分かれた地上デジタル放送の帯域の1つ(1セグメント)を使い、映像・音声・データを放送することから、「ワンセグ」と呼ばれています。
基本的に12セグメントを使って送り出される通常の地上デジタルテレビ放送に比べ、解像度は「320×180」と小さいものの、簡易な情報処理と低消費電力という特徴を活かし、外出先でテレビ放送の受信が可能です。
もちろん番組は無料で視聴できます!
ワンセグは、通常の車載テレビ向けの地上デジタルテレビ放送の拡大と共に順次視聴エリアが広がっています。
ワンセグは、移動体向けの地上デジタル放送です。今までの地上アナログ放送の走行中の受信で起こりやすかったゴーストや映像のちらつきなどがなく、電波の弱い場所でも安定したテレビ映像を実現します。今まで映像が乱れやすかったスポーツ番組などがワンセグチューナーを使えば、鮮明な画質で楽しめます。
ワンセグは通常の地上デジタル放送(12セグ)に比べデータ量が軽く、広い範囲に電波が届くので、走行中でも安定した受信が可能となりました。市街地・高速道・高架下などの電波状態がよくない場所を走ることが多いクルマに最適なテレビ放送です。
Posted by mikoqi at
16:44
│Comments(0)